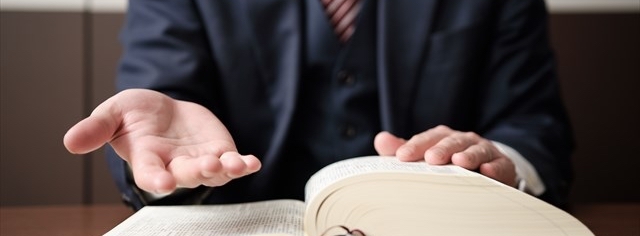
キャッチコピー
テキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキスト
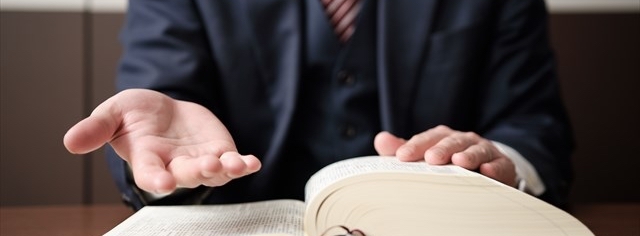

将来に向けて準備をしたいがどのような制度を利用してよいのかわからない、
「成年後見制度」「民事信託」など、聞いたことはあるがどのような場面で利用をしてよいかわからないなど、
どのような制度・サービスがあるのか、どのような場面で利用するものなのか、わからないという方も多いかと思います。
ここでは、まず、どのような制度があり、それぞれどのような特徴があるか、簡単に説明をさせて頂きます。
目次
1 はじめに
2 成年後見制度(法定後見制度)
3 任意後見制度
4 民事信託
5 日常生活自立支援事業
6 財産管理契約(財産管理委任契約)
7 各制度の比較
ご高齢の方・障がいのある方の財産管理・契約支援の制度として、一般的には、以下のような制度、サービスがあります。
① 成年後見制度(成年後見・保佐・補助)
② 任意後見制度(任意後見契約)
③ 民事信託(「家族信託」と呼ばれることもあります。)
④ 日常生活自立支援事業
⑤ 財産管理契約(財産管理委任契約)等
これらの制度をどれを利用すべきかは、何を目的にするか、現在のご本人の状況はどのようなものなのかによって利用する制度が異なってきます。また、事案によっては、複数の制度を併用することもあり得ます。
ここでは、まず、それぞれの制度を簡単に説明させていただきます。
成年後見制度(法定後見制度)とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方の財産の管理や契約手続の支援などを行うことにより、そのような方を保護、支援するための制度です。家庭裁判所によって選ばれた(成年)後見人・保佐人・補助人という方が、ご本人のために、不動産や預貯金などの財産を管理し、必要に応じ遺産分割などの必要な手続きを行い、介護サービス・施設入所・病院入院などの必要な契約を結び、書類の作成や費用の支払等の事務を代行します。また、ご本人が悪徳商法の被害にあっている場合などは、後見人・保佐人・補助人がその契約を取り消すなどします。このように、判断能力の不十分なご本人を守り、支援するのが成年後見制度です。
より詳しくは、別の記事でご案内をさせて頂きます。
本人が元気な(十分に判断能力を有している)間に、将来のために、自身の財産の管理などをお願いする人(任意後見人)との間で契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分となった後、契約に従い任意後見人が本人のために契約に定められた業務を行うという制度です。①の法廷後見制度と異なり、だれを後見人にするか、どのような業務をお願いするかは、本人が契約により決めることが可能です。また、法廷後見制度同様、家庭裁判所(及び後見監督人)の監督が入ることも特徴です。
任意後見制度の特殊性として、契約は必ず公正証書で締結しなければならないこと、契約の効力を生じさせるために家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をしなければならないこと、契約の効力発生後は必ず任意後見監督人が選任される(報告義務や監督人の報酬の問題が発生する)ことなど、利用のためには一定の手間や費用がかかります。
「法定後見制度」は、家庭裁判所が事案に応じ、ご本人のために適切な後見人・保佐人・補助人を選ぶ制度です。一方「任意後見制度」は、ご本人が元気(十分な判断能力を有している)うちに自身の(任意)後見人になってもらう方と契約を結んでおき、ご本人の判断能力が不十分になったときにその方に(任意)後見人に就任してもらう制度です。
両制度一番大きな違いは、後見人等となる方を自分で選ぶか家庭裁判所が選ぶかという点にあります。また、後見人等の権限の範囲も任意後見制度の場合は契約で決める一方、法定後見制度の場合は家庭裁判所が決めることになります。なお、どちらの制度を利用した場合も、後見人等の最終的な監督は家庭裁判所が行います。
法定後見制度と任意後見制度の違いは、以下のとおりとなります。
| 法定後見制度 | 任意後見制度 | |
|---|---|---|
| 誰が後見人等を選ぶか | 家庭裁判所 | ご本人 |
| 後見人等の権限の範囲 | 家庭裁判所が決める | ご本人と任意後見人との任意後見契約で決める |
| 手続きの方法 | 家庭裁判所に申し立てる | ① 判断能力があるうちに任意後見契約を締結する ② 判断能力が低下したら家庭裁判所に後見監督人選任の申立てを行う |
| 家庭裁判所の監督 | ある | ある |
| 後見監督人 | 選任される場合と選任されない場合がある | 必ず選任される(任意後見監督人の報酬も発生する) |
| 後見人の報酬 | 家庭裁判所が決める | 任意後見契約で決める |
本人(委託者)が、自身の特定の財産を、信頼できる人(受託者)に預け、契約に定めた目的に従って管理、活用等をお願いするという制度です。誰が利益を受けるか(受益者)も契約によって定めることができます。信託の内容は契約によって定めることになるため、成年後見制度と比べ、より柔軟に財産管理の内容を定めることができます。また、成年後見制度は財産を「守る」ことが主になりがちですが、信託では、財産を「運用」することを主目的とすることも可能です。
一方で、民事信託の場合、成年後見制度のように、判断能力が不十分になった後に契約手続等を代行してもらうといったことはできません。また、成年後見制度のような裁判所による監督がないため、委託者自身で信頼のできる受託者を探す必要があります(信託契約等により信託監督人を設定することは可能です。)。ご家族など、近しい人に信頼のできる方がいらっしゃればよいのですが、そのような状況がなければと使うことは難しい制度となります。なお、法律上、原則として、弁護士などの専門職が、報酬を受けて信託を受けることはできません。
各地の社会福祉協議会が提供するサービスで、本人が、契約により、社会福祉協議会に預貯金の管理や定期訪問などの業務を委託するものです。社会福祉協議会との「契約」であるため、利用のためには「契約」を理解できるだけの能力が必要となります(判断能力が低下した場合には、成年後見などへの切り替えが必要となります。)。サービスの利用の可否は社会福祉協議会が判断することになっています(審査会などが設置されています。)ので、だれでも利用できるということではありません。
利用の可否、業務の内容、利用料(1回の訪問につき1000円程度としているところが多いと思われます。)などについては、各市町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。
自身の財産を、契約により、預かってもらうものです。とくに定義が決まっているものではないため、法律に反しない限り、自由に契約内容を定め、契約をすることができます。ただし、「契約」であるため、「契約」の内容を理解できるだけの判断能力が求められること、通常、監督者がいないため、不適切な管理が行われるリスクがそれなりにあることに注意をする必要があります。また、金融機関などの内規、運用によっては、財産管理契約を締結した第三者による預金の引出し等を認めないこともあります。
最後に、各制度の比較すると以下のようになります。
| 成年後見制度 (法定後見) | 任意後見制度 | 民事信託 | 日常生活 自立支援事業 | 財産管理契約 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受託者 | 裁判所が決める | 契約で決める | 家族など | 社会福祉協議会 | 契約で決める |
| 本人の契約能力 | 不要 | 契約時に必要 | 契約時に必要 | 必要 | 必要 |
| 契約書の作成方法 | 契約書不要 | 公正証書限定 | 公正証書が望ましい | 社会福祉協議会の書式 | 制限なし |
| (家庭)裁判所の関与 | あり | あり | なし | なし | なし |
| 監督者 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 後見監督人 | なし、又は 信託監督人 | 社会福祉協議会の審議委員会など | なし |
| 業務内容 | 財産管理 身上監護 | 財産管理 身上監護 | 財産の管理・運用等 | 財産・書類の管理等 | 契約内容による |
それぞれの制度は、重なり合う部分もありますが、異なっている部分も多くあります。目的に応じ、適切な制度を使い分けることが重要です。また、目的によっては、複数の制度を併用することもあり得ます。
どの制度をどのように利用することが適切か、専門家への相談をお勧めします。
成年後見制度・財産管理等のご相談・ご依頼をお考えの方は、南池袋法律事務所にご連絡ください!
03-6709-3638
受付:平日・土日祝日 10:00〜21:00
初回相談無料 全国受付